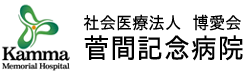リハビリテーション科について
当リハビリテーション科では、急性期から回復期、維持・在宅期までの幅広い期間、そして様々な疾患に対応しており、入院早期から各専門職がチームとして関わり、質の高いリハビリテーションを提供できるよう心がけています。入院でのリハビリテーションの他に、外来リハビリテーションをはじめ、訪問や通所リハビリテーション、ショートステイでのリハビリテーションを実施しており、退院後の生活においても十分なサポート体制を備えています。また、地域での介護予防教室や、法人運営のフィットネスクラブでのスタジオプログラム、自治体運営の介護予防施設への出向、医療・介護職へのリハビリテーション研修会の開催など地域での活動にも力を入れています。

新卒者から中堅・ベテランまで、和気あいあいとしていて和やかな雰囲気のリハビリテーション科です
リハビリテーション科の理念
常に高い志を持ってリハビリテーションを提供し、地域の皆様に貢献します。
リハビリテーション科の基本方針
1、発症直後から在宅まで、一貫性のあるリハビリテーションを提供します。
リハビリテーションを必要とするすべての患者に対し、発症直後から計画的・組織的に実施し、在宅生活に導くため の取り組みを重視します。必要があれば、外来通院、通所リハビリテーション、訪問などの後方施設に繋げ、在宅復帰後も悪化することの無いよう支援します。
2、チームアプローチで最大限の効果を発揮します。
地域の中核となる病院として、各専門職が常に連絡を取り合い、詳細な計画に基づいたチームアプローチを実践し、 質の高いリハビリテーションを提供いたします。
3、周辺の関連機関との連携を重視します。
退院後も最良な状態で継続的に在宅生活を送ることができるよう、住宅改修や福祉用具の選定、リハビリテーショ ン・介護指導のみならず、居宅介護支援事業所、訪問及び通所事業所との連携も重視し、最大限のリハビリテーショ ン支援を行います。
4、予防的指導、教育啓発活動へも積極的に取り組みます。
超高齢社会における課題である「健康増進」、「介護予防」、「地域包括ケア」を重視し、様々な機会に地域における教育啓発活動を行います。また、そのための知識・技術の獲得を怠りません。
スタッフの行動指針
- 社会人としての常識を持ち、職場の秩序を守ります。
- 誠実な態度で仲間に接し、互いに助け合います。
- チャレンジ精神を持ち、積極果敢に行動します。
- 患者さんに寄り添い、親切な態度で接します。
- 自ら知識・技術の向上に励み、専門性を高めます。
- 仲間同士率直に意見を交換し、互いを高め合います。
- リハビリテーション科の一員としての役割を果たし、質の向上に貢献します。
- 院内・外の他職種と積極的にコミュニケートし、連携を推進します。
- 住民の健康に関心を持ち、地域での活動に参加します。
- 体調管理に留意し、心身共に健やかに働きます。
施設基準
| 施設基準 |
|---|
| 心大血管リハビリテーション(Ⅰ) |
| 脳血管疾患等リハビリテーション(Ⅰ) |
| 運動器疾患リハビリテーション(Ⅰ) |
| 呼吸器リハビリテーション(Ⅰ) |
| がん患者リハビリテーション |
理学療法
理学療法部門では、脳血管疾患や整形外科疾患、心疾患、呼吸器疾患、がんやその他消化器疾患の術後の方、神経難病など、幅広い方を対象とし、身体機能、移動能力等が低下した患者様に対して運動療法や物理療法を通して、機能回復を図っています。発症または術後早期からすみやかに介入し、患者様に適したアプローチを検討し実施しています。身体機能の回復を図るとともに福祉用具や住宅改修、退院後のリハビリテーションの助言も行い、より良い形で社会復帰できるよう支援しています。また、各種疾患や障害に対する外来理学療法も積極的に受け入れています。

当院における理学療法士の役割(入院)
- 入院により活動範囲が狭まり、身体機能が低下している人または低下が懸念される方に対して、入院早期から離床をはかり、廃用症候群を予防します。
- 入院による二次的な障害(褥瘡、転倒、転落)が懸念される方に対して、看護師と協働し、予防対策を講じます。
- 身体機能の低下により日常生活動作に支障をきたしている方に対して、物理療法、運動療法により身体機能回復を支援します。
- 基本動作能力の低下により日常生活動作に支障をきたしている方に対して基本動作練習を実施し、動作獲得を目指します。
- 退院後の心身機能低下・基本的動作能力の低下が懸念される方に対して、自主運動の指導や後方支援担当者への情報提供等、退院後の重度化予防のための支援を行います。
- 緩和ケア期にあり、身体的苦痛(痛み、息苦しさ、だるさ)が生じている方に対して、緩和的理学療法を実施します。
作業療法
作業療法部門では、脳梗塞等の脳血管疾患や骨折等の整形疾患、神経難病などにより、身体機能面・心理社会機能面・高次脳機能面等が低下した患者様に対してリハビリテーションを行っています。
日常生活動作(食事・整容・更衣・入浴・排泄といったセルフケア)や家事動作の練習から就労支援に至るまで幅広いリハビリを行い、その人らしさを引き出し、楽しみが持てるよう工夫しながら訓練をしています。また、各種疾患や障害に対して外来での作業療法も積極的に行っています。

当院における作業療法士の役割(入院)
- 落ちこみのある・気持ちが塞いでいる方に対して、本人の辛い事や不安に寄り添い心や体が動くように支援します。
- 認知機能の低下がある方に対して、本人の興味や残存記憶を引きだし笑顔が増えるように支援します。
- 作業活動に興味がある・趣味がありそうな方に対して、その方に最適な作業活動を提供します。
- 身の回り活動・家事活動・社会活動等の再獲得にひと工夫が必要な方に対して、自助具・指導道具の検討、動作方法の工夫と助言、動作練習を通して獲得を支援します。
- 上肢機能に問題がある方(脳梗塞や手の手術をした人等)に対して、治療物品(ペグ・セラバンド・巧緻機能)を使用しながら、直接的・間接的動作練習を行い作業目標が達成できるよう支援します。
- 高次能機能障害がにより身の回り動作等に支障をきたしている方に対して、対応方法を検討し実行します。
- 緩和ケア期にあり精神的苦痛のある方に対して、緩和的作業療法を実施します。
言語聴覚療法
言語聴覚療法部門では、脳血管疾患等によって起こるコミュニケーション障害や神経難病、摂食嚥下機能障害の患者様に対してリハビリテーションを行っています。
急性期から回復期、生活期において、患者様の状態や状況に応じて、障害された機能の改善をめざす治療の他に、障害した機能を他の手段で補う練習を行い、患者様が円滑に日常生活を送り、希望のある生活を取り戻せるように支援しています。また、各種疾患や障害に対して、外来での言語聴覚療法も積極的に行っています。

- ムセる、痰がらみ、飲み込みに時間がかかるなど食べる機能に問題がある方に対して、その方に適した誤嚥しない食形態、介助方法を決定します。
- 聞く、話す、読む、書くに問題(失語症、構音障害など)がある方に対して、失語症と構音障害の鑑別を行い、言語訓練を実施し、コミュニケーション環境を調整します。
- コミュニケーションに影響する高次脳機能障害がある方に対して、対応方法を検討します。また、認知症との鑑別を行います。
- 緩和ケア期にあり、心身的苦痛のある方に対して、緩和的言語聴覚療法を実施します。
リハビリテーションの流れ
当院における入院早期から回復期、退院後までのリハビリテーションの基本的な流れを紹介させていただきます。
処方
医師からリハビリテーションの指示が出ます。

「早めにリハビリを始めましょう」
急性期リハビリテーション
各病棟に配置されたスタッフが、発症や手術後すみやかにリハビリをはじめます。

集中治療室での運動療法

言語聴覚士との摂食・嚥下療法
地域包括ケア病棟、療養病棟
病状が安定した後、在宅復帰支援を目的とした地域包括ケア病棟、療養病棟に転棟し、集中的に各種リハビリを行います。

理学療法士との運動療法

作業療法士との日常生活動作練習

集団体操

作業活動
退院に向けて
退院後安全に生活ができるよう、作業療法士等が退院前にお宅にうかがい住宅改修や福祉用具を検討し、退院時にはご家族や介護保険スタッフを交えてカンファレンスをおこないます。

退院前訪問指導

退院カンファレンス
退院後のリハビリテーション
退院後も継続してリハビリテーションが必要な方は、当院での外来リハビリテーションや併設する在宅総合ケアセンターからの訪問リハビリテーション、通所リハビリテーションが受けられます。

外来リハビリテーション

訪問リハビリテーション

通所リハビリテーション
配置図
当リハビリテーション科では、診療班ごとのチーム制を採用し、臨床、教育、学術活動を協力しながら行える体制となっています。
| 配置部署 | 理学療法士 | 作業療法士 | 言語聴覚士 | |
|---|---|---|---|---|
| 菅間記念病院 | 管理者 | 1 | ||
| 中央棟理学療法 | 9 | 8 | 6 | |
| 東棟理学療法 | 10 | |||
| 医療療養病棟 | 2(兼務) | |||
| 外来リハビリテーション | 4 | |||
| 在宅総合ケアセンター | 訪問看護ステーション | 7 | 1 | |
| 通所リハビリテーション | 7 | 1 | 2(兼務) | |
| 短期入所生活介護 | 3(兼務) | |||
| 計 | 39 | 9 | 7 | |